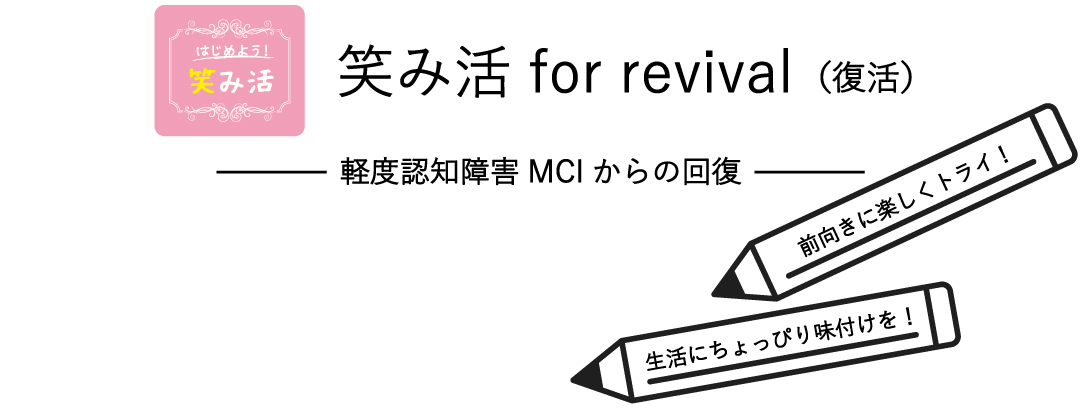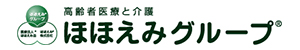今回から4回にわたり、株式会社千成の副社長、播磨様による健康コラムをお送りいたします。
今回はその1回目、日本食についてです。
主に「和食」のルーツについて、振り返ってみたいと思います。
今から1万年以上昔の縄文時代には小学校で学んだ「貝塚」から縄文式土器が沢山発掘されています、その形状から、食材を煮たり、茹でたり、加熱して食べていたと考えられています。
貝塚からはその名の通り、あさり、しじみ、蛤等の多種にわたる貝殻が見つかり、貝類を煮て食べていたのは明らかですね。
貝類にはコハク酸と言う旨味成分があり、あさりの味噌汁とか私も大好物なのですが…そう考えると縄文人は意外にグルメだったのかも?知れませんね。
又、縄文時代後期には、中国や朝鮮半島より稲作が伝来したと言われています、但し、当初は気候の変動や技術の進歩が伴わず、自然の作物や狩猟により得た食料が不足した時の予備食として、お米が扱われていたそうです。
その後、弥生時代になると稲作技術も向上して、日本全国に稲作が浸透し、現在の様にお米が、漸く、「日本人の主食」になったと言われています。
飛鳥・奈良時代になると、その後の日本人の食事に大きな影響を与える事案が起こったのです。
それは壬申の乱で有名な天武天皇により「牛馬犬猿鶏の肉を食うことなかれ、もし犯す者あれば罰せむ。」と言う、何とも仰々しい「肉食禁止令」が発令されたのでした。
これにより人々は主に魚や大豆などから、必要なタンパク質を補っていたみたいですね。
肉が食べれない為、出汁の発見に加え、盛付への工夫やこだわりが相まって、後世に世界的な健康食と謳われる「和食」の進化に繋がったのだと思われます。
日本独自の出汁文化については室町時代初期には昆布出汁、その100年後には鰹出汁が生まれ江戸時代に入った頃には、現在に近い…合わせ出汁が取られるようになったとされています。
これも日本が四方を海で囲まれた小さな島国である上に、豊富で新鮮な海産物や山の幸に加え、四季折々の食材が採れたのも、和食の進化には欠かせない要素ですね。
その後、質素倹約の風潮を背景に、精進料理や懐石料理が誕生して行きました。
考え方によっては、肉食禁止令もいい意味で日本食の発展に一役買っていたみたいですね。
自由にお肉を食べれなかった当時の人々には大変申し訳ありませんが…それから長い時を経て、肉食が解禁になるのは、明治維新を迎えた時のことです。
又、次回に振り返ると致します。

これは認知症の前段階の一つですが、日々の生活の改善や趣味活動、運動、リハビリで回復する可能性(復活)があります。
幅広く多くのことを前向きに楽しく続けていくことが大切です。
生活習慣病、減塩の日本食、地中海食、DASH食、赤ワイン、コーヒー、果物、キノコ類、サプリメント、腸内細菌、コミュニケーション、読書、知的活動、ストレスフリー、カルチャーセンター、脳トレ、ボードゲーム、スマホゲーム、有酸素運動、筋トレ、指先運動、アロマ、音楽、楽器、カラオケ、補聴器、睡眠、三日坊主歓迎